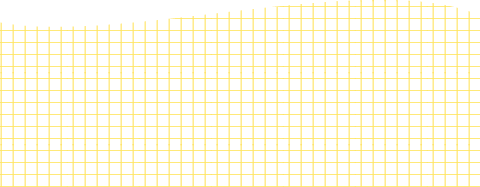ホーム > 食品添加物Q&A
(Q&Aは順次追加する予定です。なお、わかりやすくするため厳密ではない表現を使用した部分もございますので、あらかじめご了承ください。)
2024年3月1日改訂
1.食品添加物とは
食品衛生法では、食品添加物とは、食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するものと定義されています。
豆腐を作るのに「にがり」が使われたり、コンニャクを作るときに「消石灰」が使われたりしてきました。この豆腐やコンニャクは中国から伝えられて1000年以上経っているといわれています。
この「にがり」や「消石灰」は食品添加物であり、豆腐やコンニャクを作るときにどうしても欠かせないものとして現在も使われています。
食品添加物にはそれだけ長い歴史があると考えられます。
食品添加物は、次のような目的で使われるものです。
・食品を製造または加工するときに必要なもの
・食品を形作ったり、独特の食感を持たせるために必要なもの
・食品の色に関するもの(色をとったり、着けたりするもの)
・食品の味に関するもの(うま味、甘味、酸味等の味を付けるもの)
・食品の栄養成分を補うために必要なもの
・食品の品質を保つために必要なもの
日本では、食品添加物の安全性と有効性を確認して国が指定した「指定添加物」、長年使用されてきた天然添加物として品目が決められている「既存添加物」のほかに、「天然香料」や「一般飲食物添加物」に分類されています。
今後、新たに使われる食品添加物は、天然・合成の区別なく、すべて食品安全委員会による安全性の評価を受け、国の指定を受け「指定添加物」になります。
| 食品添加物 | 指定添加物(476品目) | 国が指定した添加物 |
|---|---|---|
|
・天然香料 ・一般飲食物添加物 |
いわゆる天然添加物 |
(令和6年3月12日現在)
「食品添加物にかかわる法律」のところで説明しますが、食品添加物として使えるものは、原則として全て国が指定することになっています。この食品添加物として指定された食品添加物を指定添加物といい、リスト化され、品目が決められています。これには、合成添加物もいわゆる天然添加物も区別がありません。
昔の法律では、合成添加物だけが指定されていましたが、今はいわゆる天然添加物も含む形で指定されています。
長年使用されてきた天然添加物としてリスト化され、品目が決められています。
植物、動物を基原とする香料で、約600品目が例示されています。
通常は食品として用いられるが、食品添加物的な使い方をするもので、約100品目が例示されています。
それ自身をそのままで食べることができるもの又は調理をすることによって食べることができるものが食品とされています。
食品添加物は、食品を作ったり、保存したりするために一定の目的をもって意図的に使われるものです。
このために食品添加物は、「食品添加物にかかわる法律」の項で説明する一般飲食物添加物を除けば、通常はそれ自身を食品として食べることはありません。
食塩やしょう油は伝統的に「食品」として扱われています。食品に味を付与する機能は、食塩やしょう油の本来の機能と考えられます。
2.食品添加物にかかわる法律
食品添加物は、食品衛生法という法律で定義されています。
この法律の規定に従って、食品衛生法施行令、食品衛生法施行規則、食品・添加物等の規格基準等で、食品添加物にかかわるさまざまな取り決めが定められています。
食品衛生法では、食品添加物を単に「添加物」といいます。これは、食品衛生にかかわる添加物は、食品添加物に限られるので、単に「添加物」といえばわかるからです。
食品衛生法第4条第2項で、「この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。」と定義されています。
食品衛生法では、食品添加物として次の4種類に分類されています。
・指定添加物
・既存添加物
・天然香料
・一般飲食物添加物
食品衛生法では、食品添加物に関して決められていることのうち、主なものは、次のようなことです。
・用語の定義(この法律で使う言葉の決まり)
・指定されたもの以外の添加物の販売、製造、輸入、使用などの禁止
これが食品添加物の指定制度に当たります。
・添加物の基準、規格の制定
これによって、食品添加物の使用基準、製造基準、保存基準および成分規格が制定されます。
また、基準に反した使い方や、規格に合わない添加物の販売、使用などが禁止されることになります。
・食品や食品添加物に関する表示の基準の制定
これによって、表示の仕方が決められます。
・食品添加物公定書の作成
・食品衛生管理者の設置
等
Q2に示した添加物の他に、次のような用語が定義されています。
・食品:薬事法で決められた医薬品と医薬部外品を除いたすべての飲食物
・天然香料:動植物から得られたもの又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物
・いわゆる一般飲食物添加物:一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用されるもの
他にも容器、包装、営業、販売などの用語が定義されています。
日本では、原則として使用が認められる食品添加物(天然香料及び一般飲食物添加物以外のもの)を個々に指定し、指定されてない食品添加物を食品に使用することを禁ずる方法が採用されています。
このように使用することができるもののリストを作って公表する方法をポジティブリスト方式といいます。世界的に見たとき、日本が最初に取り入れた方法で、今では、ほとんどの先進国が採用しています。
この食品添加物の指定は、内閣総理大臣が、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、人の健康を損なうおそれがない場合として定めることになっています。
既存添加物は食品衛生法の条文の中では定義されていません。平成7年の食品衛生法改正に伴う附則第2条で、既存添加物名簿に記載する添加物として次のような説明が行われています。
・既存添加物:この法律(食品衛生法等を改正する法律)の公布の際(平成7年5月24日)に、現に販売、製造、輸入、使用等が行われている添加物
同じ附則の第3条では、既存添加物並びにこれを含む製剤又は食品には、食品添加物の指定制度を適用しないと定められています。
日本の食品添加物の指定制度は、長い間、対象を化学的合成品に限っており、天然物から取り出される食品添加物は規制していませんでした。
1995年(平成7年)に、天然系の添加物を含む全ての食品添加物を指定する現在の制度に移行するとき、それまで使用してきた天然系の添加物を続けて使うことを例外的に認めるために採用されたのが、この既存添加物の制度なのです。ですから、食品衛生法の条文としてではなく、Q7でふれたように、改正のときに附則として認めた形になっています。
一般飲食物添加物とは、「一般に食品として飲食に供される物であって添加物として使用されるもの」をいいます。これは、通常は食品として食べられるものを、食品添加物と同じような働きを期待して食品の製造などに使用する場合、食品衛生法では食品添加物として扱うことになります。
通常食品である果汁等を食品の着色に使うとき、また、小麦粉や寒天を酒類の製造でろ過しやすくするために加えるときなど、さまざまなものが該当します。その主なものは、リストに挙げられています。
多くの指定添加物には、成分規格といって、国によって、含量や成分に関する規格が定められています。既存添加物や一般飲食物添加物では、約220品目に成分規格があります。
これらは、「食品,添加物等の規格基準」という規則(厚生労働省告示)で定められています。このうち、食品添加物の成分規格や基準類をまとめたものが、「食品添加物公定書」といい、現在、第9版が使用されています。
成分規格が決められている食品添加物は、規格に合うものだけが使えることになっています。
既存添加物では、約100の品目に、まだ、成分規格が決められていません。成分規格のない食品添加物は、製造する者が責任を持って品質を管理することになっています。
日本食品添加物協会では、既存添加物とよく使われる一般飲食物添加物にも、規格があることが望ましいと考えて自主的な成分規格を検討しています。その結果をまとめて日本食品添加物協会の自主規格として公表しています。
現在、89品目の自主規格を収載した「第6版既存添加物自主規格」を公表しています。
食品添加物公定書には、食品添加物の成分規格とこの規格にかかわる通則、一般試験法、試薬・試液等の他に、次の基準類が収載されています。
・製造基準:食品添加物及び食品添加物の製剤を製造するときに守らなければならない基準
・使用基準:食品添加物及び食品添加物の製剤を使って食品を作る時に守らなければならない対象食品や量に関する基準
・表示基準:食品添加物及び食品添加物の製剤を販売する時に、製品に表示する内容を決めた基準
・保存基準:Q13参照
保存基準は、製造基準、使用基準のようにまとめられたページはありません。保存基準が設定されている場合は、個々の成分規格の後に保存基準として記載されています。これは、保存方法が成分規格に大きな影響を与えるためと、保存基準が設定されている品目が、次の13品目と少ないことによります。
アセトアルデヒド、β-アポ-8’-カロテナール、エルゴカルシフェロール、β-カロテン、カンタキサンチン、コレカルシフェロール、DL-酒石酸カリウム、ナタマイシン、ナトリウムメトキシド、二炭酸ジメチル、ビタミンA油、粉末ビタミンA、メタ酒石酸
食品への食品添加物の表示につきましては、「食品表示法(平成27年4月1日施行)」に定められております。
なお、食品添加物の表示に関しては、「食品での食品添加物の表示」で詳しく説明します。
食品や添加物の製造または加工の過程で、特に衛生上の考慮が必要な場合に、その製造等の施設で、食品衛生法または食品衛生法に基づく命令や処分に対する違反が行われないように、製造または加工の従事者を監督する人です。
食品添加物に関しては、法律で成分規格が設定されている品目を製造する施設で置く必要があります。
食品衛生管理者は、次のような特別の資格を持った人に限られます。
①医師、歯科医師、薬剤師または獣医師
②大学などで、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学または農芸化学を履修して卒業した者
③厚生労働大臣が指定した食品衛生管理者の養成施設で所定の過程を修了した者
④食品衛生管理者を置いている施設で、衛生管理に3年以上従事して、厚生労働大臣の指定する講習会の過程を終了した者
日本食品添加物協会では、④にかかわる講習会に参画しています。
食品添加物の取り扱い・製造に係る法令には、労働安全衛生法(安衛法)、化学物質排出把握管理促進法(化管法)、毒物及び劇物取締法(毒劇物取締法)、消防法等があり、各々の法令に該当する食品添加物については、届出、表示(GHS対応)、文書交付(SDS)等の規制の対象になりますので、関係法令の確認が必要となります。
また、製造等に当たっては省エネや公害防止等に係る法令など、これ以外にも関連する法令がありますので、ご留意の上適切な対応をお願いします。
3.食品添加物の有用性
食品添加物として指定されるためには以下の条件があります。
(1)安全性が実証または確認されるもの
(2)使用により消費者に利点を与えるもの
①食品の製造、加工に必要不可欠なもの
②食品の栄養価を維持させるもの
③腐敗、変敗、その他の化学変化などを防ぐもの
④食品を美化し、魅力を増すもの
⑤その他、消費者に利点を与えるもの
(3)既に指定されているものと比較して、同等以上か別の効果を発揮するもの
(4)原則として化学分析等により、その添加を確認し得るもの
「食品添加物とは」のQ3で示した目的を次に示します。このような目的を満足させる機能を持つものが、食品添加物として使われます。
・食品を製造又は加工するときに必要なもの
・食品を形作ったり、独特の食感を持たせるために必要なもの
・食品の色に関するもの(着色料、漂白剤、発色剤等)
・食品の味に関するもの(甘味料、酸味料、苦味料、調味料等)
・食品の栄養成分を補うために必要なもの
・食品の品質を保つために必要なもの
完成した食品では、わからないものがほとんどですが、食品をつくるときに必要なもので、多くは製造用剤と呼ばれるグループに入る食品添加物です。これらには、酸・アルカリ、ろ過助剤、清澄剤、イオン交換樹脂、消泡剤、抽出溶剤、触媒等があります。
たとえば、サトウキビから砂糖を取り出して精製して製品の砂糖にするまでには、アルカリや酸、ろ過助剤、イオン交換樹脂等が使われます。これらが、食品を製造・加工するときに必要とされるものです。
豆腐は、原料となる豆乳に「豆腐用凝固剤」というグループの食品添加物を使用して、豆腐の状態に凝固させています。この凝固剤がないと豆腐は作れません。このようなものが食品の形を作るのに必要な食品添加物です。
他にも、菓子を作るときの「膨張剤」、中華めんに必要な「かんすい」、マーガリンなどのような乳化した食品に使われる「乳化剤」などがあります。
ゼリーやプリンは独特の食感があります。このような食感を出すためには、食品を単に固めるだけでなく、望まれる食感を持たせる必要があります。このために、ゲル化剤が使われます。
見ただけで食欲を左右するほど、食品の色はその「おいしさ」と密接な関係があります。そのため、食品をよりおいしく味わうためには、食品が適切な色であることが求められます。このために、色に関わる食品添加物が使われています。その代表は、着色料です。その他に、漂白剤、発色剤などがあります。
食品の「味」は、食品の「おいしさ」に最も貢献します。この味に関係する食品添加物には、次のようなものがあります。
・甘味料:食品に甘味をつける。
・酸味料:食品に酸味をつけたり、酸の強さを調節する。
・苦味料:食品に独特の苦味をつける。
・調味料:食品にうま味等をつける。
この他に、食品に香りをつける「香料」も使われます。
食品は、原材料を調理・加工するとき、原材料が持っていた栄養成分がなくなったり、減ったりすることがあります。このような栄養成分を補ったり、栄養価を高めたりする目的で使用されるものが、栄養強化剤とも呼ばれる食品添加物です。
この食品添加物は栄養成分の補填・強化を目的として使用され、中には、粉ミルクを母乳の成分に近づけるために使われる食品添加物も含まれています。
食品は、保存している間に微生物によって腐敗したり、油脂成分が変化したりして、食べられなくなったりすることがあります。このような品質への影響を防ぐ目的で使用される食品添加物には次のようなものがあります。
・殺菌料:加工食品の製造に先立って、原材料に付着している微生物を殺菌・除去するために使用します。
・保存料:食品中の微生物やカビの繁殖を防ぐ目的で使用します。
・酸化防止剤:油などの酸化による変質を防ぐ目的で油脂の多い食品などに使用します。
・防かび剤:果物でのカビの発生を防ぐ目的で主にかんきつ類に使用します。
・日持向上剤:保存料ほど効果が強くありませんが、短期間、品質を保つ目的で使用します。
4.食品添加物の安全性
食品安全委員会において一日摂取許容量(ADI)の設定などの安全性の評価を行い、消費者庁はその評価結果を受け、食品衛生基準審議会において審議され、日常の食事を通して摂取される食品添加物がADIを十分下回るように、使用基準などを定めるなど安全性の管理を行います。
新たに食品添加物として指定する場合、Q1で述べたように、まず食品安全委員会において安全性の評価を行った後、消費者庁、食品衛生基準審議会において審議され、摂取される食品添加物がADIを十分下回るように、安全性の管理を行います。
安全性の審議を行う際には、国際的な食品添加物の評価機関である国際連合のFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の安全性評価の結果も参考にします。
食品添加物指定に際しての検討で要求される安全性の資料には、次のようなものがあります。
1.毒性に関する資料
・反復投与試験(繰り返し食べさせたときの影響の確認)
・生殖毒性試験,発生毒性試験(次世代への影響の確認)
・発がん性試験
・アレルゲン性試験(アレルギーを発症する可能性の確認)
・遺伝毒性試験(遺伝子や染色体などへの影響の確認)
・一般薬理試験(試験された動物の生体機能に対する影響の確認)
2.体内動態に関する資料(体内でどう変化して代謝されるかの資料)
3.1日の摂取量に関する資料
Q3の1に示したようないろいろな安全性試験の結果を検討したなかで、実験動物に毒性の影響を与えない量(最大無毒性量)を求めます。次に、この最大無毒性量から、人が一日にその量以下ならば食べても有害ではない量、一日摂取許容量(ADI:Acceptable Daily Intake→Q6を参照)を求めます。
人間と実験動物では、物質に対する感受性が異なります。また、人の間でも差があります。そこで、動物実験で得られた最大無毒性量に、安全係数(Safety Factor→詳しくはQ5を参照)1/100をかけて得た値を、安全量とみなします。この安全量を参考に、使用できる食品と使用できる量を決めた使用基準を設定します。
毒性に関する試験にはいろいろな動物が使われますが、多くは、ラットやマウスのような小動物です。同じ動物といっても、このような試験結果を、人にそのまま当てはめることはできませんが、人と実験動物の感受性の差が10倍を超えることはないという経験則をもとに、人へ当てはめるときは動物実験から得られた無毒性量の1/10にします。
さらに人でも男女・老若、大柄な人・小柄な人というように、同じ人間同士でも感受性の差がありますが、その差が10倍を超えることはないという経験則をもとに、さらに1/10にして、全体で安全係数を1/100にして安全性を確保しているのです。
ADIは、Acceptable Daily Intakeの略で、一日当たり許容摂取量といいます。このADIは、Q4,Q5で説明した安全量を、一日当たりの平均値に換算して、さらに体重1kg当たりとして表したものです。
このように決められたADIですので、毎日一生涯その量をとり続けても安全な量になっています。
人は、毎日いろいろな食品を食べていますので、たまたま一日だけこのADIを越えて摂取したからといって心配する必要はありません。
5.食品での食品添加物の表示
容器包装入りの加工食品では、表示すべきことがさまざまに決められています。これらを一括して記載してある部分に、原材料名という目があります。食品添加物は、原材料名と別途に設けられた「添加物」という項目に表示されるか、「添加物」の項目を設けない場合は原材料名欄中に「/(スラッシュ)」等により原材料と食品添加物を明確に区分して表示されます。
食品添加物は、原則として使用した食品添加物を表す「物質名」で表示されます。そのうち、使用目的を表示した方が、消費者の購入の判断に役立つとされたものは、「用途名」という使用目的を表す名称も併記することになっています。
また、同種の食品添加物を複数使う場合で、個々の成分を表示する必要性が低いもの、食品中にも常在成分として存在するもの等は、まとめて「一括名」というグループ名での表示が認められています。
加工食品の製造に使われた食品添加物は、全て表示することが原則とされていますが、その食品で効果を有さないようなものは、表示が免除されています。それには、次のようなものがあります。
・加工助剤に該当する食品添加物
・キャリーオーバーに該当する食品添加物
加工食品を作るのに使われた食品添加物のうち、次の条件のいずれかに合うものが加工助剤とされます。
①最終的に食品として完成する前に、食品から除去されるもの
②食品中に通常存在する成分に変えられ、かつ、その成分の量が食品中に通常存在する量を有意に増加させないもの
③最終食品中に、ごくわずかなレベルでしか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの
その食品添加物の使用基準で、最終食品の完成前に除去あるいは分解または中和することが定められているもので次のようなものが該当します。
亜塩素酸ナトリウム、アセトン、イオン交換樹脂、塩酸、過酸化水素、次亜塩素酸水、シュウ酸、臭素酸カリウム、水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、二酸化ケイ素、ヘキサン、ポリビニルポリピロリドン、硫酸
ただし、除去又は中和という使用基準にかかわらず、水酸化カリウムは例外で、物質名で表示されます(食品表示基準について(加工食品)1義務表示事項(4)添加物、③ その他 ケを参照)。
使用基準では決められていないが、次のように、Q5と同じような使い方がなされるものも、加工助剤になります。
・使用基準では決められていないが、食品の製造・加工の工程でその食品添加物が除去あるいは分解または中和されるもの
・使用基準では決められていないが、食品中に通常存在する成分に変えられ、かつ、その成分の量が食品中に通常存在する量を有意に増加させないもの
・食品の製造・加工の工程で使用した食品添加物で、食品に残留するが、その量が少なく、その成分が食品で機能を発揮しないもの
食品の原材料の製造・加工で使用されたもので、その食品の製造には使用されない食品添加物で、最終食品まで持ち越された場合に、最終食品中では微量となって、食品添加物そのものの効果を示さない場合をキャリーオーバーといいます。
食品には、製造者の連絡先など表示すべきことがいろいろと決められていますが、表示のスペースが限られた食品では、全てを記載することが困難な場合があります。そこで、表示面積が小さい場合には、原材料の表示を省略することが認められています。表示の可能な面積が30平方センチメートル以下の場合が、食品表示法における省略の基準に該当します。
食品の原材料表示に食品添加物の名称として使用できるものは、以下のとおりです。
・品名:指定添加物の告示名称および既存添加物などの収載品目リストの品名欄に収載された名称で、いずれも別名を含む
・簡略名:表示のために品名を簡単にした名称
・類別名:本質が共通するいくつかの品目をグループとしてまとめた表示のための名称
例を挙げると、次のようになります。
| 品名 | 簡略名・類別名 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | 別名 | 簡略名 | 類別名 |
| β-カロテン | β-カロチン |
|
|
| トウガラシ色素 |
|
|
|
食品に表示すべきことはたくさんありますので、限られたスペースにどれだけ表示できるかも大切です。このため、簡単にできるものは、できるだけ簡単にすることを目的として作られたものが、簡略名と類別名です。
「β-カロテン」のβ-や「DL-アラニン」のDL-のような異性体を示す符号を省略したり、「亜硝酸ナトリウム」を「亜硝酸Na」で表すようにカリウム、カルシウム、ナトリウム、マグネシウムを、元素記号のK,Ca,Na,Mgで置き換えたり、「クエン酸三カリウム」を「クエン酸カリウム」および「クエン酸K」とするように置換数を省略したりします。
既存添加物では、この他に「カフェイン(抽出物)」などの(抽出物)を省略することもあります。また、その主要な成分名を簡略名としたものもあります。
Q9の物質名の例にあった「カロテノイド」などのように、異なったものでも本質は変わりがない場合があります。このように同じようなものをまとめても、表示の目的には反しないとして、まとめられたものが類別名です。
類別名は、着色料に多く認められいます。
現在の食品添加物の全面表示を方向付けた1988年の食品衛生法施行規則改正までは、一部の食品添加物に限って、主に使用目的を示す名称で表示されていました。そのため、消費者などの強い要望もあり、それまで使われてきた表示を残す形で、用途名になったのです。
現在、併記する用途名は、次のように8種類あります。
甘味料、着色料、保存料、糊料(または、増粘剤・安定剤・ゲル 化剤)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(または、防ばい剤)
この中で、糊料はそのグループ全般に使える用途名ですが、増粘剤は増粘の目的、安定剤は安定させる目的、ゲル化剤はゲル化の目的で使用した時に限って使われる用途名です。
防かび剤と防ばい剤は、漢字で書くと防黴剤となるもので、読み方の違いによって2つの用途名になったものです。
原則は併記ですが、併記しなくても使用目的が判る場合は、用途名を省略できます。省略ができるのは、次のような場合です。
着色料:色という文字があるとき
たとえば、カロテン色素やカロテノイド色素のようなもの
増粘剤:増粘多糖類と表示するとき
ゲル化の目的で使用したときは、「ゲル化剤(増粘多糖類)」となります。
Q10~Q12で説明した簡略名や類別名は、食品添加物を物質として考えて作られたものですが、一括名は、食品添加物の使用目的でまとめられたものです。表示のスペースも念頭に置いて、類別名と同じように認められたものです。
一括名には、食品衛生法施行規則の改正が行われたときに、多くの消費者に知られていた使用目的を示す名称が採用されました。
現在認められている一括名は、次の14種類です。
イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、乳化剤、酸味料、チューインガム軟化剤、調味料、pH調整剤、豆腐用凝固剤、膨張剤、香料
このうち、調味料は、アミノ酸、核酸、無機塩、有機酸の4つのグループに分けられており、これらのグループ名を併記します。
チューインガム軟化剤と豆腐用凝固剤は、それぞれ、軟化剤、凝固剤と表示することができます。
膨張剤は、膨脹剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉とも表示することができます。
一括名に関しては、消費者庁の次長通知(「食品表示基準について」)で、その定義と一括名を使用できる食品添加物が決められています。このため、同じような目的で使用しても、一括名の範囲に入っていない食品添加物の場合は、物質名で表示することになります。
逆に一括名の定義外の目的で使う場合も、物質名で表示することになります。
6.食品添加物の国際的関係
国際的には、食品添加物の安全性の検討や成分規格の設定等科学に基づいたリスクアセスメントを担当する国連の下部組織にJECFAという組織と、食品添加物の使用基準の設定等のリスクマネージメントを担当するCCFAという組織があります。
CCFAは、国際的に流通している食品の規格を検討しているCAC(通常、コーデックスと称している)の下部組織です。
JECFAとは、FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additivesの略で、国際連合食糧農業機関(FAO)と国際連合世界保健機関(WHO)の合同食品添加物専門家会議を意味します。食品添加物の安全性の評価、成分規格等に関する検討を行うために、FAOおよびWHOが食品添加物にかかわる安全性(毒性)と規格に関する専門研究者を指名して組織する会議です。
これらの研究者は純粋に専門家として参加し、国あるいは団体を代表する立場をとらないことが定められています。
CACとは、FAO/WHO Codex Alimentarius Commission の略で、合同食品規格委員会と呼んでいます。消費者の健康を保護し、食品の貿易に係る公正を保証することを目的に、各国の国内事情によってまちまちになっている食品に関するさまざまな決まりに、国際的な整合性を持たせるための政府間協議機関であり、その成果は国際食品規格集としてまとめられています。
CCFAとは、Q3のCACの下部組織で、Codex Committee on Food Additives の略です。この委員会は、CACの食品全般に係わる課題を扱う全般問題部会に属し、食品添加物に関する検討を行う委員会で、食品添加物部会と訳されています。食品添加物使用の原則、使用基準、食品分類等の検討を行っています。
EU(欧州連合)でも、ヨーロッパでの食品添加物に関する共通の規則をまとめている機関(EFSA)があります。
7.食品添加物にまつわる疑問
野菜中には硝酸塩が多く含まれており、野菜の摂取後、体内で硝酸塩の一部は亜硝酸塩に変換されます。亜硝酸塩、硝酸塩は、野菜由来の摂取が添加物由来よりも多いことが知られています。野菜由来でも添加物由来でも、科学的には同じものなので、添加物として亜硝酸塩等を摂取してもそのために身体に悪影響が出るということはありません。 一方、野菜はビタミンやミネラル、食物繊維等の摂取源として有用ですので、いろんな種類を適度に摂取するべきと考えます。
FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)は食品添加物の亜硝酸ナトリウムによる発がんリスクを評価しており、ヒトの摂取と発がんリスクとの間に関連があるという証拠はないとしています。<参考:食品安全委員会HP、ハザード別の情報「亜硝酸塩等の発色剤」>
(硝酸塩、亜硝酸塩が胃の中でニトロソ化合物になった場合について)
国際がん研究機関(IARC)は、胃の中で硝酸塩または亜硝酸塩がニトロソ化を起こす場合について、おそらくヒトに対して発がん性ありとし、グループ2Aに分類しています。IARCの分類については、発がん性の「ある/ない」を示すものであり、発がん性の強さや摂取量等に基づく「リスクの大きさ」は考慮されていないことに注意が必要です。
リンは人が摂るべき栄養素の一つであり、肉や野菜に含まれています。食事で摂るリンのうち、食品添加物由来のリンはとても少ないことから、通常の食事であればリンの過剰摂取になることはないと思われます。
日本人の食事摂取基準において、リンの耐容上限量(※1)は3000mg/日とされています。過去の国民健康・栄養調査から、日本人のリン摂取量は980mg前後/日である一方、食品添加物由来のリンの摂取はその数%(※2)というレベルです。リンは動植物の生体成分として肉や野菜にも含まれており、通常の食生活においては食品添加物由来のリンによってリンの過剰摂取になることはないと思われます。例え耐容上限量3000mg/日に近い量を摂取する人がいるとしても、その場合、過度な食事量や偏った栄養摂取による他の影響も考慮するべきと考えます。
※1 ほとんど全ての人に健康上悪影響を及ぼす危険がない栄養素の1日当たりの最大摂取量のこと
※2 参考:日本透析医会雑誌 Vol.30 No.3 512-518(2015)
ソルビン酸やその他の塩類が遺伝子を突然変異させることはなく、よって身体への影響はありません。
ソルビン酸カルシウムが新規指定される際、食品安全委員会が、ソルビン酸及びその他の塩類の試験成績を用いてグループとして食品健康影響評価を実施し、2008年に厚生労働省で添加物評価書として報告しています。その結論として、特段問題となるような遺伝毒性※はないとされています。<参考:食品安全委員会HP、ハザード別の情報「ソルビン酸カルシウム」>
※物質が直接的又は間接的にDNAに変化を与える性質のこと
ソルビン酸と亜硝酸塩の併用によるヒトの健康に対する悪影響はありません。ご質問の情報は、2008年の食品安全委員会によるソルビン酸カルシウムの添加物評価書の記載を元に、誤って伝えられているものです。食品安全委員会は、ソルビン酸と亜硝酸塩の併用について、通常条件下ではヒトの健康に対する悪影響はないと結論付けています。
2008年の食品安全委員会によるソルビン酸カルシウムの添加物評価書には、ソルビン酸と亜硝酸塩の共存下の加熱試験反応によりDNA損傷物質が産生されることが報告されている旨の記載がありますが、続く記載では、この結果が特別なin vitroにおける実験条件下(亜硝酸ナトリウムとソルビン酸の共存溶液を90℃の湯煎で1時間加熱)で得られたもので、ソルビン酸と亜硝酸ナトリウムが食品中に共存した場合に形成されることを意味するものではない、とされています。食品安全委員会は、ソルビン酸と亜硝酸塩の併用について、通常条件下ではヒトの健康に対する悪影響はないと結論付けています。<参考:食品安全委員会HP、ハザード別の情報「ソルビン酸カルシウム」>
過去に一部メディアにおいて、ご質問のようなことが報道されました際、食品安全委員会が反論コメントを公表しております。上記内容は、そのコメントに沿ってまとめています。
現在、食品添加物の着色料として使用が認められているタール色素12品目において、発がん性の疑いのあるものは有りません。
合成系の着色料であるタール色素は、過去にその安全性等の見直しにより、いくつかの品目は削除されました。最後の削除は、昭和40年代まで遡ります。現在使用が認められているタール色素は、食品添加物として適切に使用する限り、発がん性等の安全性の問題はありません。タール色素使用商品排除を宣言している小売店も散見されますが、現在使用が認められているタール色素の発がん性等の根拠を持ち合わせていないものと思われます。
なお、食用青色1号、食用緑色3号、食用赤色40号、食用黄色4号について、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)において再評価中(※)でしたが、2018年3月までに終了し、これまで通り使用可能と判断されています。
※ 評価時期が古いもの等について、新しく提出されたデータによる再評価
本情報は、イギリスの大学が発表した論文が元になっていると思われます。EU、米国、オーストラリア・ニュージーランドによるリスク評価においては、タール色素の摂取と子供の注意欠陥・多動障害との因果関係が確認できず、当該論文は根拠にならないとされています。
ご質問の内容は、イギリスのサウサンプトン大学が2004年と2007年に発表した論文が元になっていると思われますが、根拠として支持されていないというのが現在までに各国で行われた検証状況です。
欧州連合(EU)は2008年に発効した添加物規制において、一部の色素製品に警告文「子供の活動や注意に悪影響を及ぼす可能性がある」を付けることを要求しましたが、その後、リスク評価機関である欧州食品安全機関(EFSA)は、2009年と2010年に意見書を公表し、入手可能な証拠が、色素暴露と行動への影響の可能性との因果関係を支持しないと結論付けています。
米国食品医薬品局(FDA)の委員会は、2011年、サウサンプトンの研究を含めたデータは、食用色素の摂取と多動性への影響の間の因果関係を支持しないと結論付けました。
オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、サウサンプトン研究が、食用色素の安全性の評価を変える(より厳しくする)根拠にならないことを示しました。
<参考:食品安全委員会HP、食品安全総合情報システム「オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食用色素についてのファクトシートを公表」>
人工甘味料等の食品添加物は、様々な論文等を基に複数の専門家による審議を経て、安全性が確認されています。一部の論文データを根拠にネガティブな情報が発信されるケースが散見されますが、不安をあおって注目を集めようとしている場合があり、注意が必要です。
科学者が他の研究者による国内外の研究論文を基にその内容が全てであり正しいかのように発信していることがありますが、食品添加物をはじめ化学物質の安全性については、複数の専門家によりできるだけ多くの論文やデータを検証することを以って論じられることが必要です。(※)
食品添加物としての認可取得以降も多くの安全性情報が発信されており、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)や欧州食品安全機関(EFSA)等の公的機関による安全性の再評価が実施されています。
※ 例えば、2014年にNature誌から「Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota」と題された論文が発表され、メディアは人工甘味料が糖尿病を促進するかもしれないと科学者が主張していると報じました。これに対し、英国のNHS(国営保健サービス)や各国の科学者は、本研究が主にマウスでのものであることと、ヒトの試験もされているが7人と少なく1週間での結果であること、実際はいくつか試験した甘味料のうちサッカリンのみの結果にも関わらず人工甘味料を一括りにして論じられていることを指摘し、本研究を人工甘味料による糖尿病促進の根拠とみなしておりません。<参考:国立医薬品衛生研究所HP、食品安全情報(化学物質)No. 20/ 2014(2014. 10. 01)>
食品添加物の調味料が味覚障害を起こしたり、味覚を衰えさせる という科学的根拠は見当たりません。
なお、化学調味料という法令用語はなく、何を指すのかあいまいな情報のまま、これまで口承されてきたものです。
「化学調味料」の正式な定義はありませんが、多くの場合、食品添加物の調味料に該当するものを指しています。
本件について、いわゆる化学調味料によって味覚障害になったり、味覚を衰えさせることを支持する論文やデータが見当たっておりません。
わたしたちの口の中には、食べ物の味を受け取る「味細胞」と呼ばれる細胞がたくさん存在しています。この味細胞は一定期間内で新しい細胞と入れ替わります。そのため食品添加物の調味料を常時使用することにより味覚障害がおきることはありません。<参考:うま味調味料協会HP、よくある質問>
食品添加物によって亜鉛の吸収が阻害されて味覚異常を起こすという科学的根拠は見当たりません。
当協会では加工食品中の食品添加物によって亜鉛の吸収が阻害されることの具体的な根拠が示されたものを確認できておりません。
一方、亜鉛の吸収は、植物由来の食品に含まれるフィチン酸や、カルシウム、乳製品、食物繊維、コーヒー、オレンジジュース、アルコールなどで阻害されることが知られています(※1)。また、吸収過程で2価の陽イオンである鉄や銅などと拮抗します(※2)。
※1 亜鉛欠乏症の診療指針2016(一般社団法人 日本臨床栄養学会)より引用
※2 日本人の食事摂取基準2015(厚生労働省)より引用
カラメル色素に発がん性ありとの情報は、一部のカラメル色素に4-メチルイミダゾールという物質が副産物として含まれていることによります。
4-メチルイミダゾールは、カラメル色素由来の摂取量では発がん性はありません。従って、食品に使用されるカラメル色素による発がんの心配はありません。
カラメル色素にはⅠ~Ⅳの4つあり(※1)、ⅢとⅣにおいては、製造過程で4-メチルイミダゾール(4-MEI)という副産物が生成されます。海外でマウスの試験で、4-MEIによるがん発生率の上昇がみられましたが、この試験での4-MEIの投与量が人が摂取する推定量をはるかに超える量だったことなどから、食品摂取における発がん性の根拠とされていません。
4-MEIは、コーヒー豆の焙煎や肉を焼くなど、通常の調理でも生成されるもので、食事からとる量をゼロにすることはできません。食品添加物のカラメル色素の4-MEIにおいては、規格基準で上限値を定めることで、リスク管理されています。(※2)
※1 I~Ⅳは、いずれも炭水化物を原料につくられるもので、製造過程で使用する他の原料などの違いにより、特性などが異なるものですが、いずれも食品を褐色に着色する目的で使用されています。
※2 「食品添加物公定書」にて、カラメル色素の規格基準が定められています。
加工デンプン11種類は、平成20年の食品添加物としての新規指定時に、食品安全委員会により評価されていますが、発がん性が認められたものはありません。
加工デンプン11種類(※1)は、平成20年の食品添加物としての新規指定時(※2)に、食品安全委員会により評価されています。評価書には、発がん性の根拠となるような記載内容は有りません。加工デンプン11種類が添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、ADI(1日摂取許容量)を特定する必要はないと評価されました。
加工デンプン11種類のうち、ヒドロキシプロピルデンプン及びヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプンについては、欧州連合において、これらの製造工程で使用されるプロピレンオキシドや副生成物等の安全性情報が不足していることから、乳幼児食品への使用は適切でないとされています。食品安全委員会において、日本における推定摂取量に基づく発がんの生涯リスクを導いたところ、一般に遺伝毒性発がん物質の無視しうるレベルとされる100万分の1レベルを下回っていること等から、そのリスクは極めて低いと考えられた、との見解が示されています。
※1 11種類は、いずれもデンプンを原料に加工を行ったもので、製造過程で使用する他の原料などの違いにより、分子構造や特性が異なるものです。食感改良、粘度安定性付与、乳化安定性付与など、広範な目的で使用されています。
※2 食品添加物は、食品衛生法第6条によって健康のおそれのないもののみ使用が認められています。発がん性やその他の健康被害の可能性のあるものは、使用は認められないことになります。
食品添加物は消費者に何らかのメリットを与えるものですが、健康を損なうおそれが無いことが必須です。
食品添加物として使用を許可される前に、発がん性の有無も調べられます。
発がん性ありとされたものについては、食品衛生法のもと、食品添加物として許可されません。
当Q&Aページの「4.食品添加物の安全性 Q3 安全性試験にはどのようなものがありますか?」のAでお答えしていますように、食品添加物の指定のためには発がん性試験が実施されます。試験結果の検証により、発がん性ありと判断されたものについては、食品添加物としては許可されません。(※)
既にリストにある食品添加物においても、海外での再検証による試験結果や国内での試験結果などによる新たな知見からの検証により、食品添加物として許可されなくなる例もあります。最も新しい例は15年以上遡り、2004年のアカネ色素の消除でした。これはいわゆる天然添加物として使用されてきたもので、1995年の食品衛生法改正により後追いで安全性が確認されていたものです。現在では、予め安全性を確認されることなしに食品添加物としては許可されません。
※ 平成8年の厚生省(現:厚生労働省)の局長通知により、食品添加物の指定において必要な試験が示されており、発がん性試験も含まれています。また、食品添加物は、食品衛生法第6条によって健康のおそれのないもののみ使用が認められています。発がん性やその他の健康被害の可能性のあるものは、使用は認められないことになります。
食品添加物は消費者に何らかのメリットを与えるものですが、健康を損なうおそれが無いことが必須です。
食品添加物として使用を許可される前に、体内に蓄積することがないかも調べられます。
体内への蓄積がみられるものについては、食品衛生法のもと、食品添加物として許可されません。
当Q&Aページの「4.食品添加物の安全性 Q3 安全性試験にはどのようなものがありますか?」でお答えしていますように、食品添加物の指定のためには体内動態を調べる試験が実施されます。体内への蓄積の有無も調べられます。試験結果の検証により、代謝されずに体内へ蓄積されると判断されたものについては、食品添加物としては許可されません。(※)
※ 平成8年の厚生省(現:厚生労働省)の局長通知により、食品添加物の指定において必要な試験が示されており、体内動態試験(体内でどう変化して代謝されるかの試験)も含まれています。また、食品添加物は、食品衛生法第6条によって健康のおそれのないもののみ使用が認められています。体内への蓄積やその他の健康被害の可能性のあるものは、使用は認められないことになります。
複合影響により、健康被害が起きる可能性は非常に低いです。
平成19年の食品安全委員会報告書において、「起こり得る可能性は極めて低く、現実的な問題ではない」旨が示されており、日常摂取している範囲内では健康への影響はほとんどないといえます。
食品添加物は、ヒトの身体に影響の出ない量しか摂取されないように使用基準が定められています。および、蓄積性がないことも確認されています。医薬品の場合は、ヒトの身体に影響を及ぼす量を摂りますので、複数を同時に摂取することなどで思わぬ影響が出る場合があります。しかし、何の影響も出ないものを、何種類同時に摂っても、理論的には影響が出ないものと考えられます。
食品安全委員会の調査報告書から抜粋します。「以上のことから、食品添加物の複合暴露による健康影響については、多数の添加物が使用されていても、実際に起こりうる可能性は極めて低く、現実的な問題ではなく、理論的な可能性の推定にとどまるものである。ただちにリスク評価を行う必要のある事例も現時点ではなく、個々の添加物として評価されている影響を超えた複合的な影響が顕著に出ている事例は見出されなかった。現在、食品添加物はADI の考え方を基本として個別に安全性が審査されているが、複合影響の可能性を検討する際にもこのアプローチは有効であり、個々の食品添加物の評価を十分に行うことで、食品添加物の複合影響についても実質的な安全性を十分確保することが可能であると考えられた。」
調査報告書には、続いて下記のようにも記載(抜粋)されており、今後も消費者の不安を払拭するための取り組みが必要とコメントされています。「食品添加物の複合暴露による健康影響については、現実的な問題ではなく、理論的な可能性の推定の範囲にとどまるものと考えられたが、安全性にさらに確実を期し、消費者の不安を払拭するための取り組みは今後も必要である。」
身近な話として、通常の食事中には、多種多様な成分が混在しており、それらによる相互作用についての懸念はなく、検証もされていません。食品添加物についても、微量の使用ということもあり、食事中の成分と同様に相互作用による影響の懸念はないと言えます。
国ごとに食品添加物の定義や範囲が異なるため、数の比較は困難です。日本の食品添加物の数が突出して多いことの根拠はありません。
例えば、香料を食品添加物に含めるかどうかは国によって異なります。日本では香料は食品添加物なので、そうでない国と比較して、香料分だけでも数百種類の差が出ることになります。このように、一概に揃えて数を比較することは難しく、日本の食品添加物の数が多いという根拠はありません。
一部のネット等の情報で、海外の添加物の数が「米国が約130種、ドイツ32種、イギリス21種」のような記載がありますが、根拠が不明で参照に値しないものです。
また、食品添加物の許可数と体への影響に関係性は無く、それよりも、個々の食品添加物の性質や使用方法、使用量等に着目することで自身が食している食品に対する正しい理解につながると思われます。
海外で安全性等の懸念により新たに食品添加物が禁止等の規制がされた場合、日本においてもその食品添加物に対する科学的評価の上、何らかの対応が検討されます。
一方、各国の法規制が異なるため、自国で食品への使用が許可されている食品添加物が、他国で使用不可の場合はあります。(「禁止」ではありません)
「禁止」という言葉は、安全性の懸念からかつて使用できたものを禁ずるような印象を与えます。しかし、実際には最初から使用許可を求められていない場合(上記「使用不可」の意)が多いです。
例えば、日本ではいわゆる天然添加物(既存添加物)が多く使われていますが、海外では使用できないものが多くあります。これは、日本国内で独自に開発され、海外では使用されてこなかったものが多いからです。食品添加物の規制は国ごとに実施されており、使用されない食品添加物について安全性の評価は行われないために、使用できない状態となっています。
日本では天然由来の方がイメージが良いとされること、以前は化学合成品のみが食品添加物としての規制対象とされていたことから、多くのいわゆる天然由来の添加物が開発されました。これらの多くは国際的には使用されておらず、従って食品添加物としての使用許可申請をされることもなく、今でも日本以外では使うことのできないものが多くあります。
このように、各国の食文化により使われてきた食品添加物はまちまちであり、必要性が無かったため最初からリストに無い食品添加物もそれぞれの国にあります。
海外で新たに食品添加物が禁止あるいは何らかの規制がされた場合、その内容によって、管理省庁が日本の食品添加物に対して何らかの規制をすることもあります。個々の食品添加物の安全性評価は、食品安全委員会が担います。
トランス脂肪酸は食品添加物ではなく、牛肉等に微量に含まれるほか、一部の油脂の製造工程において生成することが知られているものです。
トランス脂肪酸の摂取量は各国の食生活により大きく異なり、摂取量の多い国ではトランス脂肪酸を多く含む油脂の食品への使用を規制しているところがあります。
日本においては、トランス脂肪酸の摂取量が低いことから規制の必要がないとされています。
トランス脂肪酸の過剰摂取は冠動脈疾患を増加させる可能性が高いこと等から、WHOはトランス脂肪酸摂取を総エネルギー摂取量の1%未満とすることを目標にしています。
トランス脂肪酸の平均摂取量はアメリカと日本とでは大きく異なり、アメリカでは2.2%、日本では0.3%とされています(いずれも総エネルギー摂取量比)。しかも日本国内で流通するマーガリンやショートニングなどに含まれるトランス脂肪酸は、製造方法の改善などで過去約10年間で10分の1前後に減少しています。
日本ではむしろ飽和脂肪酸の摂取量に注意が必要とされており、トランス脂肪酸低減により飽和脂肪酸含有量が増加する傾向にあることも考慮されて、部分水素添加油脂(※)への規制は導入されていません。
なお、「トランス脂肪酸が海外で使用禁止」といった表現を目にすることがありますが、トランス脂肪酸自体を食品に加えるようなことはありません。部分水素添加油脂にトランス脂肪酸が含まれることから、アメリカ等では「部分水素添加油脂の食品への使用を規制」しようとしています。
※不飽和脂肪酸に水素を付加(水素添加)する技術により製造される油脂を水素添加油脂といい、完全水素添加油脂と部分水素添加油脂があります。完全水素添加油脂にはトランス脂肪酸は含まれていない一方、部分水素添加油脂にはトランス脂肪酸が含まれることがあります。
PDFファイルを見るためには、Acrobat Readerというソフトが必要です。
Acrobat Readerは無料で配布されています。下のアイコンをクリックしてご利用下さい。